広場・エントランス他Plaza & Entrance
- 伝統芸能
- 広場
- どなたでも
- 入場無料
第17回水戸市郷土民俗芸能のつどい【第1部】
2019年2月24日(日) 10:30~12:40

水戸市内の各所には、いにしえより特色ある郷土の民俗芸能が数多く存在し、それぞれの地域へと伝えられてきました。本公演では、その技を継承してきた各団体が一堂に会し、日頃ご覧いただく機会が少ない伝統の技を披露します。
【第1部 広場】※雨天時はエントランスホールになります。
10:30~10:45 開会式
10:50~11:15 水戸太鼓
11:30~11:50 向町の散々(ささら)楽踊り
11:55~12:10 大串のささらばやし
12:25~12:40 大野のみろくばやし
【第2部 ACM劇場】
13:35~13:55 田谷の棒術
13:58~14:05 水戸盆唄
14:06~14:35 水府流水術
14:40~14:50 水戸大神楽
14:55~15:15 大根むき花
15:20~15:40 杉崎芸能保存会
15:45~15:55 閉会の挨拶
概要
会場
広場
開催日程
2019年2月24日(日) 10:30~12:40
お問合せ
水戸市民俗芸能団体協議会:029-227-6688
【主催】
水戸市民俗芸能団体協議会、公益財団法人水戸市芸術振興財団

水戸太鼓(水戸太鼓保存会)
水戸太鼓の歴史は、水戸藩第九代藩主徳川斉昭公時代、軍の演習として追鳥狩が行われ戦陣の合図として打ち鳴らされた太鼓の時代にさかのぼります。水戸の太鼓の伝統を受け継ぎ、水戸の新しい郷土芸能として昭和48年7月に創作されました。結成以来、数多くのステージで水戸太鼓を披露し、今では水戸にとどまらず茨城を代表する郷土民俗芸能として発展しております。曲は水戸の古き良き伝統と四季折々の情景を盛り込み15曲のオリジナル曲を持ち、直径3尺3寸の葵陣太鼓を打ち込んでの勇壮な演奏は大好評をいただいております。また数年前より津軽三味線を取り入れて、太鼓との競演を行い、演奏の幅も広げています。

向井町散々楽(ささら)踊り(向井町散々楽保存会)
昔、台渡里(現在の水戸市渡里町)に一盛(いちもり)長者という豪族がおり、この長者は、八幡太郎義家(源義家)が蝦夷に征伐に向かう際、10万の兵を大いにもてなしました。あまりにも豪勢なもてなしぶりに、将来わが身が危うくなるかもしれないと考えた義家は東北遠征の折に一盛長者を滅ぼしてしまいました。その時、家臣が散々楽を持ち出して、向井町に住みついたところから向井町の散々楽の名がついたと言われています。向井町の散々楽は竹棒に人形を付けたもので、「棒ささら」と呼ばれ、雄獅子・雌獅子・子獅子の3体で成り立っています。以前、東照宮のお祭りの際、露払いとして大変伝統のある行列で天狗を先頭に家内安全、厄除け、五穀豊穣を祈願して町内を歩いたと言い伝えられています。
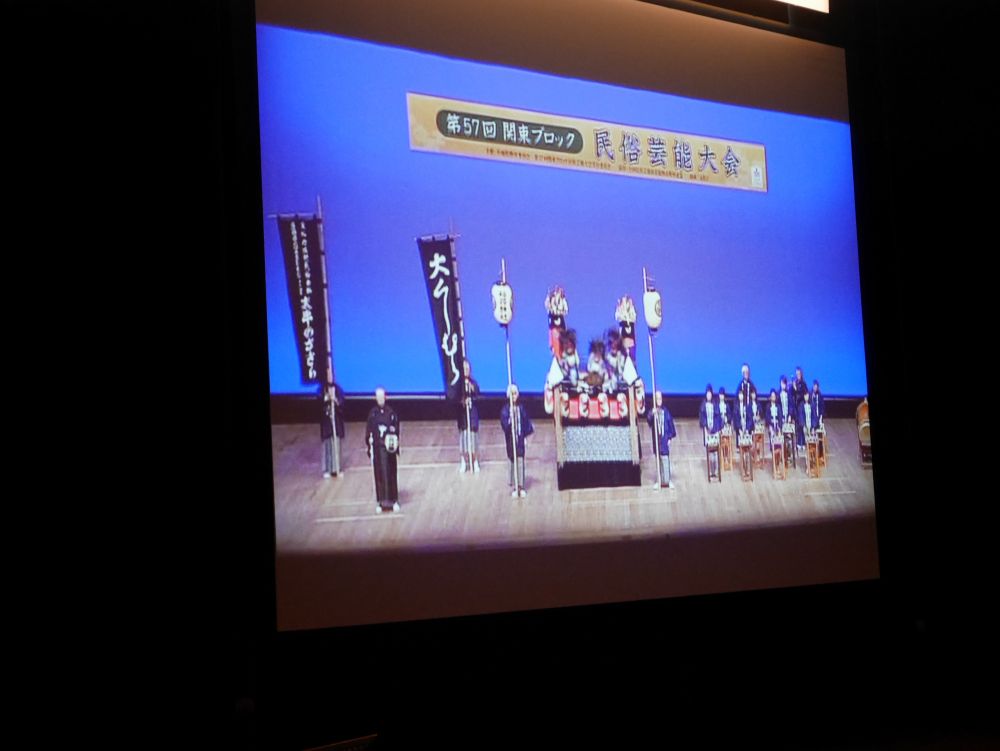
大串のささらばやし(大串ささらばやし保存会)
大串のささらばやしは大串稲荷神社の祭礼に、江戸時代中期頃から氏子たちが年番(1年交代で執務すること。)を決め、無病息災、五穀豊穣を願って、「ささらばやし」を奉納したのが起源とされています。獅子頭を棒につけて操る「棒ささら」です。四方に幕などを張り巡らし、人が中に入り、お囃子に合わせて棒を操ることで、3頭の獅子が舞うように見せるもので、3頭の獅子は雄獅子・雌獅子・子獅子で、子獅子がはぐれ、再びめぐり合うといった親子の情を表す舞が行われます。棒ささらは茨城県の水戸・石岡地区に集中し、他県には見られない全国的にもめずらしい民俗芸能です。江戸時代は寺社奉公所の所管で行われましたが、明治以後は大串で行われるようになりました。現在は11月23日の祭礼で居祭りと称し、神社境内で行われます。
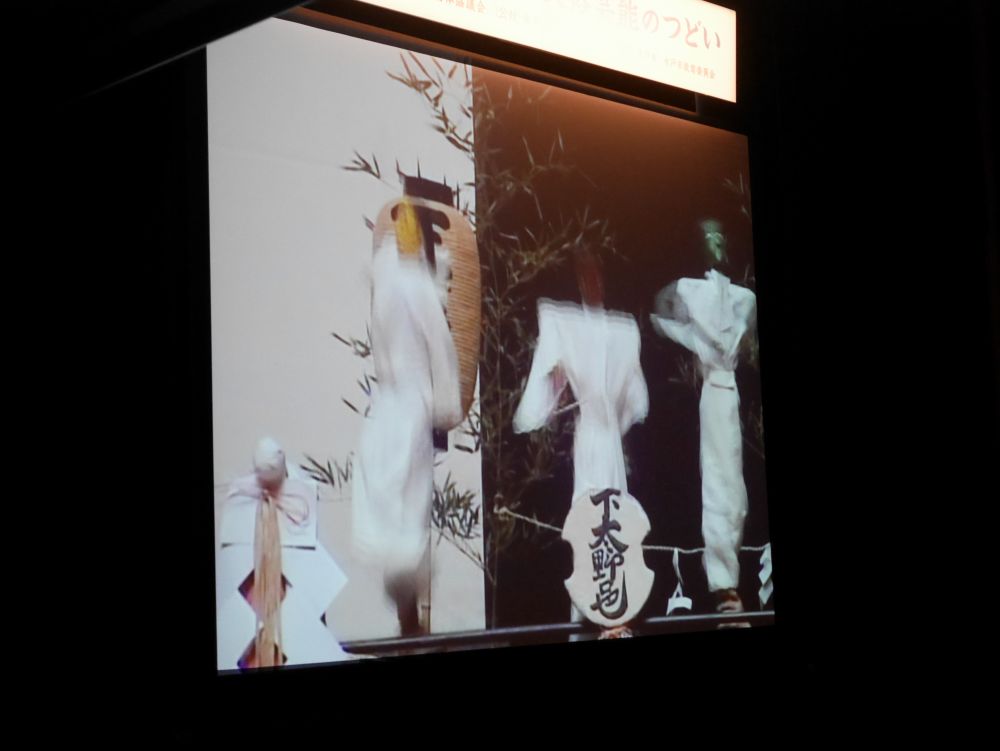
大野のみろくばやし(大野みろくばやし保存会)
お囃子にのって面白い顔をした3体のみろく人形が舞います。化粧幕で囲われた底なし屋台の中で、子どもが駄々をこねるように操り人が棒先の人形をゆすることから、別名「大野の駄々みろく」ともいわれます。青い顔が鹿島さま、赤い顔が香取さま、黄色い顔が春日さまと呼びます。みろく人形の出自は水戸藩二代藩主徳川光圀公にまつわる民話風に語り継がれてきました。元禄のはじめ、藩命によって鹿島香取神社が下大野の鎮守社として祀られていることから、鹿島信仰と弥勒信仰の習合した念仏踊りが形を変えて伝わったものと考えられます。素朴で貴重なものとの評が高まり、昭和37年に保存会を結成し、後継者育成に取り組んできました。お囃子のなかの歌の意味が分かった人は長者になるといわれています。






