- 演劇
2018-07-10 更新
水戸子どもミュージカルスクールレポート⑤
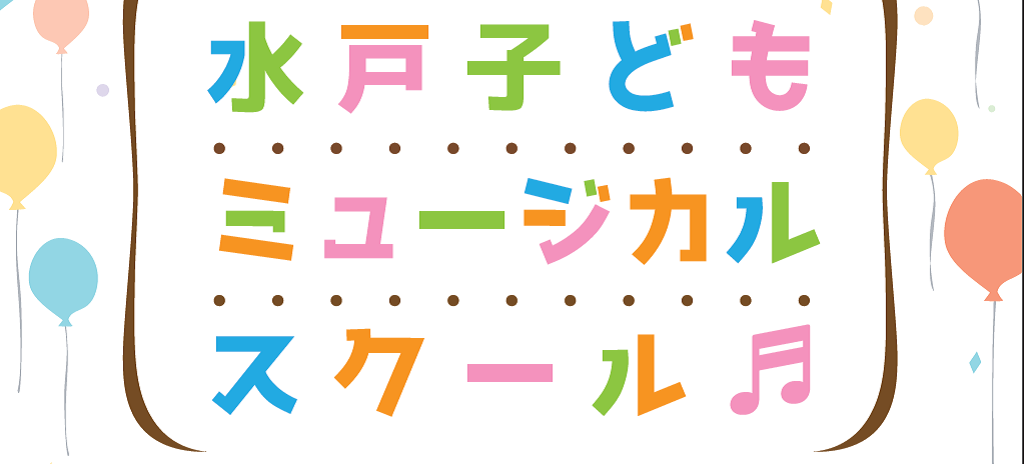
今年度で6期目を迎えた『水戸子どもミュージカルスクール』
井上芸術監督のスクールレポート5回目は、7月8日のレッスンの様子です。
========================================
夏も本格的になってきました。
メンバーもこの数回のレッスンでスクールに慣れつつ、一学期も後半という疲れも出たのか、時間ぎりぎりにスタジオに飛び込んでくる子も増えてしまいました。
余裕をもった時間のやりくりもレッスンのうちです。慌てずに落ち着いてレッスンに臨む環境を自分で作っていきましょう。
本日のレッスン開始!
今回も基本のレッスンは、ストレッチ、ステップの練習、発声、歌唱の順で行われました。
ストレッチで体をほぐしてから、ステップのエクササイズです。今回も新しいステップが加わりました。
新しいステップ、つまりそれは普段の生活の中にない動きです。
まだまだ意識と身体が連動しないので、動きそのものがちぐはぐなものになってしまいます。
その意識と身体をつなぐのが大事な作業となります。
自転車に乗れたばっかりの時は、いろんなことが一緒にできません。
次第に繰り返していけば次第に色々同時にできるようなっていきます。
しかし簡単に思えたことですら、自分が思ったよりも習得に時間がかかりますが、時間をかければ確実に上達します。
最初からうまかった人は誰もいないのです。
本人が納得できるまで何度でも繰り返して自分のものにできるのか、時間と根気が必要ですが、ここが最初の頑張りどころです。
コツコツ頑張っていきましょう!
意識と身体と声
もちろん、自分の身体がどんな状態だと一番良いパフォーマンスになるのかという意識も大事です。
声にしても、動きにしてもそれは一緒です。
高城ヘッドコーチから、「腕を動かす時にどこから動かすのか、腕の始まりはどこかと思う?」という問いが投げかけられます。
すると縮みがちな動きが、途端に躍動感のあるものとなって行きます。
ちょっとした投げかけやコツがメンバーに確実な実感を与えていきます。
こんな風にエクササイズは続いていきますが、メンバーたちの、コーチの指示への集中力と反応力は毎回確実に良くなっています。
そしてメンバー同士でも、息が合ってきたり、とっさの判断をみんなで共有できるようなったりしてきています。
どうやら何かが、少しずつ繋がってきているようです。
塩谷ヴォイスコーチからは、意識の持ち方で声が変わることを伝授されました。
また口が動くということは、筋肉の動きの結果です。ですから、その筋力アップのエクササイズも学びました。
セリフ術というと早口言葉のレッスンとか思い起こしますが、そもそも口は筋肉で動かすものだから、その筋トレというわけです。
マッチョな口になるのではないのでご心配なく(笑)。
きれいな発音が出来るようなる道のりの一つです。
増山歌唱コーチは、伴奏がなくとも常に体の中にリズムを意識して歌うように指導が繰り返されております。
最初は伴奏があって歌い、そしてアカペラで歌う。
何度かやってみて、自分たちが感じた問題を発言してもらいました。
自分のことはもちろん、チームとしての問題をしっかり発言してくれました。
歌そのものはまだまだなままですが、その発言を出来たということは、大きな前進の可能性が生まれたことも教えてくれています。
もちろん増山コーチのお手本に近づくという実践的なエクササイズも当然ありますが、大事なことは自分たちで課題を発見して、
それを自らが解決するにはどうしたら良いかを考えられるようになることです。
「気づき」と成長
コーチの皆さんは、自分たちの専門分野で、メンバーたちに
「あることが出来るようなるには、どうしたら良いのかを考えて」という投げかけを常に行っています。
それに対してメンバーは自分を見つめ、その問題点や課題を探し、そして自らが解決策を考える。
そしてコーチがそれを更にアドバイスする。
コーチに導かれつつも、いずれ自らが道を作っていくようになってほしいと思っているからです。
「自分が、自分の変化(成長)のために何をしたらよいかが分かる」というのは、学びの場ではある種の「気づき」と言われますが、これが手に入った人の成長は大きいものとなります。
今年、高城ヘッドコーチは、機会あるごとにメンバーに自主的に参加することを呼びかけています。
「自分ならどうするのか」
「自分だったらどうしたいのか」
「作品が面白くなるにはどうしたらいいんだろ」
「上達するにはどうしたら良いんだろ」・・・。
こんな風にいろいろな方向で提案してくださっています。
もちろん、やりたいことを言ってみるだけでなく、どうしたらみんなと実現できるのかを考えながらの作業です。
もちろん、どんなアイデアでも受け付ける態勢で待ち受けています!
そして前回も書いた通り「私がやらないだろうことをやって!」という高城ヘッドコーチの愉快なハードルまであります。
学びのステップと子どもたちの可能性
学びのステップはいくつかあり、色々な言い方があります。
「守破離」という言い方では、
「守」は、師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身につける段階。
「破」は、他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階。
「離」は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階です。
一般にこれは武道や芸を志した人たちに向けて言われる教えでありますが、どうやら高城ヘッドコーチはこれを一気にやってしまおうという狙いのようです。
高城ヘッドコーチは常々
「これまで参加してくれたメンバーの誰もがものすごい伸びしろを持っている。人はこんなに変わって行けるのか、伸びていけるのか」
と、その感動をよく言葉にして言ってくださいます。
そして今年は「その可能性をもっと見つめよう」とお考えいただいているものと感じております。
私たちもその考えに大いに賛成です。
ミュージカルスクールを通じて、そんな可能性が大きくなりながら、ミュージカル作りを楽しんでもらえたら、それにすぐるものはありませんから。
【記:井上桂(ACM劇場芸術監督)】
高城ヘッドコーチのコメント
今回のレッスンは、グループでの練習時間が印象に残りました。
順調に進むグループもあれば、悩み多きグループもあったようですね。
各グループがどういった進行状況でも「一生懸命考えていた」という共通点が私には見えました。
この公演コースは舞台でお客さまに観ていただくというゴールがありますから「完成する」という結果も大事です。でも、私がもっと大事にしていることは「自分で考えて、失敗したとしてもいろいろトライしてみる」というプロセスです。
どうぞたくさん失敗してください。イヤな想いも悔しい想いもたくさんして、また考えてください。
私は大人になっても未だにそれを繰り返してますが、元気に生きてますので、大丈夫!!
来週のグループ練習も楽しみにしてます。
高城信江
↓↓高城信江ヘッドコーチのブログにもスクールの様子が紹介されています!
https://ameblo.jp/niji-okurimono/entry-12381102324.html






