- 音楽
2020-01-09 更新
音楽との出会い、作曲家への道、すべて水戸から始まった
作曲家・池辺晋一郎 インタビュー
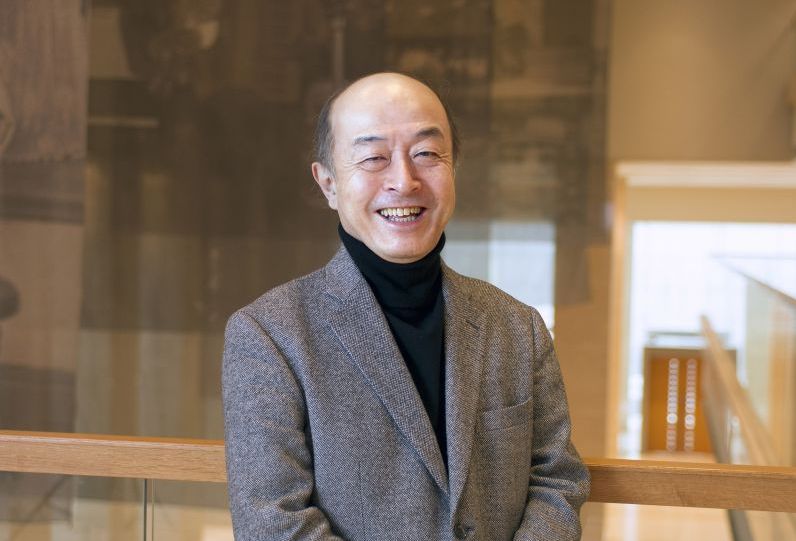
© 東京オペラシティ文化財団 撮影:武藤章
――池辺先生は、水戸に生まれ、幼少時代を水戸で過ごされています。音楽との出会いも水戸だったのでしょうか?
その通りです。母親のピアノが家にあったということと、僕は体が弱くて、戸外で遊べなかったからピアノで遊んでいたということの2つが原点ですね。体が弱くて小学校に行けずに、ひがな寝ていた小学校浪人の1年間が、おおきな転機でした。寝ていて外で遊べないから、ピアノで遊ぶ。もし体が丈夫だったら、きちんと習ったであろうピアノを、でたらめで弾くしかなかったのですが、そのでたらめというのが、作曲につながっていくわけです。ある時、僕が弾いたでたらめを、うちにピアノがあったからよく遊びに来ていた大学生が、楽譜に起こしてくれたんですよ。そしたら僕は楽譜という遊びを覚えてしまった。その大学生が、ノートに定規で5本線を引いて、音符を書いていたから、僕もそういうものかと思ってしまった。今でも1冊だけ残っていますよ、自分で5線を引いたものが。五線紙というのがあることを知らなかったんだね。
――作曲家を目指そうとお考えになったのは、いつの頃でしたか。そのきっかけは何ですか。
最初は全然、目指してなかったです。ただ一番大好きな遊びで、もうずっと毎日、曲を作っていて、次第に膨大な量になっていきました。それで水戸が関係するのですけれど、ちょうど、水戸の祖父母の家に遊びに来ていた高校1年の終わりの春休みに、水戸に当時、東京芸術大学の作曲科の4年生で、しかし、もう社会人を経験したという、かなりの年齢の先生(藤島昌寿氏)がいて、その先生のところに、母方の祖父か祖母か忘れましたが、風呂敷に包んで僕のでたらめを持って行ってしまったのです。そうしたらその先生から呼び出されて、こんなでたらめを書いていては駄目だから、勉強しろと言われ、その場で池内友次郎先生というかたに電話されて、それで突然、東京芸大を受けろと言われて、専門家を目指すことに強制的にさせられてしまったのです。余計な話ですが、実は、大好きで書いて遊んでいるだけだったしっぺ返しが、ずっと後に来るのです。大学が終わる頃、松村禎三さんのところに、よく遊びに行っていました。そうしたら、君は作曲坊やだと言われたのです。好きで遊んで書いているだけだと。僕はそれがものすごいショックで、それから2年間くらいピタッと書けなくなりました。自分で何かの主張をしなければ作品ではないと言われたのです。何も書けなかった2年間くらいの時期は、僕は大学を出ていましたから、NHKとか文学座や俳優座などの劇団などから仕事が来ていて、そういう依頼の作曲は出来るのです。しかし、ちゃんとした自分の作品が書けなくて、苦しみました。今考えれば、あの時の苦しみは、いつかは向き会わなくてはならないはずのものであったし、それを若い時に経験できたというのは、よかったと思います。松村禎三さんのおかげですよ。
――東京芸術大学に入られ、作品を世に発表されはじめた1960年代前半は、ブーレーズやシュトックハウゼンなどのヨーロッパの前衛音楽やアメリカのジョン・ケージの音楽思想などが、わが国でも注目を集めていたかと思いますが、当時、池辺先生はどのような作曲家を目指そうとされていたのでしょうか。
まだ何を目指すか分からなかった頃で、すべてにかぶれました。ちょうど東京・青山の草月ホールで前衛音楽のコンサートが開かれていて、ほとんど通いました。そして、自分で何でもやってみました。例えばコンピュータ・ミュージックも作りました。その頃はまだパソコンなんて無いから、友達の大学の大型コンピュータを借りたりしました。それからヴァレーズの〈ポエム・エレクトロニク〉というミュジック・コンクレート(具体音楽)の作品に触発されて、自分でもテープの切り貼りをして作品を作ってもみました。ドデカフォニー(十二音音楽)も書いてみたし、偶然性の音楽もやってみる。あらゆることを試みた末に、先ほどお話しした松村さんの作曲坊やの話が重なって、苦しみ抜いた2年間くらいの後に、自分がやりたいことが見えてきたのです。自分がやりたいことが見えないときは、何でもやったという気がします。しかし、それもいい経験であったと思います。
――今回の演奏会では、そうした創作初期の1960年代の作品から、まさにこの演奏会のために書き下ろされた最新の作品まで、池辺先生の創作の軌跡を辿るプログラムとなっていますが、池辺先生ご自身が、これまでの創作を振り返られて、お感じになっていることをお聞かせください。
2つのエレメント(要素)があると思っています。ひとつはハンスリック(ウィーンで活躍した音楽評論家 1825 - 1904)の音楽美論ではないけれど、純音楽というか、まったく音だけで勝負する世界。「ストラータ」というシリーズがそれにあたります。「ストラータ(strata)」というのは、「地層」を意味する「ストラートゥム(stratum)」の複数形ですが、要するに楽器の音域を地層に見立てています。楽器が持っている音域というのは、いわばその楽器の人格、つまりキャラクターであると捉え、それに焦点を当てたのが「ストラータ」というシリーズです。今回水戸で初演する〈ストラータXIII〉はフルートとクラリネットのための作品です。フルートとクラリネットのそれぞれの音域というのは数度ズレています。フルートの最高音の方が5度か6度上まで出るし、下は逆にクラリネットが5度か6度フルートよりも低くまで出る。しかし、この2つの楽器は、ほぼ同じ音域をカバーしている。その地層=音域による、音の世界を描きたいと思っています。
それから、たとえば、今回のプログラムの中に〈君は土と河の匂いがする〉とか〈大地は蒼い一個のオレンジのような…〉など、これらは僕の好きな詩の一節です。〈君は土と河の匂いがする〉はレミ・ドゥ・グルモンの詩の一節、〈大地は蒼い一個のオレンジのような…〉はエリュアールの詩です。詩が好きなので、詩からヒントを得るというか、世界が見えてくるということがよくあります。先ほどの〈ストラータ〉とは逆に、音以外の想念を音に託すというのが、もうひとつのエレメントです。〈ギターは耐え、そして希望しつづける〉というのもその一つです。僕はナチのホロコーストがあった収容所にいくつか行っていますが、アウシュヴィッツへの訪問のあとにテレジーンというプラハ郊外の収容所へ行った時に、手作りの楽器が展示されていました。それはヴァイオリンでしたが、鈴木大介君に作曲の依頼を受けた時に、ギターも収容所で手作りした人がいたに違いないと思い、そういう手作りの楽器ではあるが、そこから光が見えてくるという想いが、僕にこの曲を書かせました。ドラマや映画の音楽をたくさん書いてきたことと関わると思うのですが、音と何か別の想念を重ねるという世界が、僕は自分の中にあると思っています。音符を書いていることが、あたかもドラマを書いているかのように感じられることがよくあります。音がたとえばどこへ行きたい、ここへ行きたいと登場人物のように言ってきて、それを操作していると別の音と出会ったときに何か軋轢が起こったりするという、一編のドラマのような気がするのです。そういう癖というか、想念の組み合わせ方のシステムというものがあります。
――今回の演奏会で取り上げられる作品について、色々とお話しくださいましたが、まだ触れられていない歌曲について、ご紹介ください。
先ほどお話ししたように、音とドラマというのは自分の中でとても強い関わりを持っており、それと同一線上に歌曲もあります。先ほども言いましたが、僕は詩が好きで、僕の書棚は様々な詩集ばかりが並んでいます。歌を書くというのは、僕の中では必然的な道筋ですね。詩にアプローチすることから歌が生まれてくる。今度の2月のコンサートの少し後に、僕の歌曲集が全音楽譜出版社から出版されます。今回の演奏曲は、その歌曲集にすべて収められています。たとえば茨城出身の詩人ですけれど新川和江さんの詩には、たくさんの歌曲を書きました。〈恋する猫のセレナーデ〉と〈バラ泥棒〉はなかにし礼さんの詩ですが、なかにしさんはクラシック音楽に滅茶苦茶詳しい人で、一緒に数多くの仕事をしてきました。それから、もちろん谷川俊太郎さんともたくさんご一緒させていただいています。そういう好きな詩で書いた結果の曲が、今回のプログラムとして並んでいます。どうしてそんなに詩が好きかとよく聞かれるんですけど、その答えは簡単なんです。僕はしがない作曲家だからです。ないものねだりで、詩が好きなんです(笑)。
――今回の演奏会では、池辺先生ご推薦の素晴らしい演奏家の方々にご出演いただきます。簡単にご紹介ください。
ソプラノの小林沙羅さんは、今最も旬な日本のソプラノだと思います。僕とはたくさん関わっていて、今僕が書いている2021年12月に初演する姫路のオペラでも彼女の主役が決まっています。音楽の世界だけでなくて、この人は詩にめっぽう強くて、東京芸術大学在学中に詩の会を学内で主宰していたほどです。詩の専門誌で僕と谷川俊太郎さんとが対談をした記事が出ると、それをいち早く読んで感想を送ってきたのは、他ならぬ沙羅さんでした。知的なアプローチのできるソプラノの一人ですね。その伴奏をするピアノの河野紘子さんは、ギターの大萩康司君の奥さんです。大萩君と同じ世代のギタリストには、鈴木大介君や村治奏一君など素晴らしい人がいっぱいいますけど、大萩君は積極的なアプローチをしていて、しかも今回取り上げる僕のこの曲を物凄く研究して、肉薄している演奏家です。コンサート・シリーズのタイトルを「ギターは耐え、そして希望しつづける」にしてよいかと聞いてきました。工藤重典君は、今ここで言うまでもないくらい本当に凄いフルーティストです。もちろん僕はよく知っていますけれど、おそらく音楽の現場でお付き合いするのは初めてだと思います。とても楽しみです。亀井良信君とは何度か仕事をしていますけれど、素晴らしいクラリネット奏者です。新作の〈ストラータXIII〉について、先ほど音域に対する関心と言いましたが、この2人の演奏家の存在が作曲のモチベーションですね。それからクァルテット・エクセルシオですが、彼らに何年か前に初演してもらった弦楽四重奏曲があります。素晴らしい弦楽四重奏団で、とても期待しています。それから長田真実さんは、僕が芸術監督をしている姫路のパルナソスホールのオルガニストを務めている人です。そういうこともあって、縁がある。すべて僕が畏敬して、なおかつ友人であり、音楽仲間であり、貴重な存在と思っている演奏家ばかりです。
――池辺先生は、1990年の開館時から、水戸芸術館の活動に関わり、音楽部門の運営にご助言いただいたり、「現代音楽を楽しもう」シリーズや近年の「クリスマス・プレゼント・コンサート」など数多くの企画を実現してくださったりしています。水戸芸術館の30年間の活動ついて、どのようなご感想をお持ちですか。
水戸芸術館には、建設時からヘルメットを被って中に入っています。充実した活動で歳月を重ねてきて、30年経った。素晴らしいと思います。当初から、水戸芸術館が優れているのは、音楽ホールだけではなくて演劇と美術という3つの側面を併設させているところだと思っていました。その考えは今でも変わりなくて、この3つが連動しているということが、水戸芸術館の特質を形作っているのだと思います。しかも、室内管弦楽団と劇団がある。僕は、兵庫県立ピッコロシアターの劇団と仕事をした時に、音楽を生で入れたんですよ。それは兵庫芸術文化センター管弦楽団のメンバーで、全員ではないけれど、演劇の公演の時に生演奏をしてもらいました。それは、同じ県立で劇団とオーケストラがあるのだから、連動するべきだと言って、やってもらいました。7~8年前ですが。僕がその時によく言っていたのは、ひとつの地方自治体が劇団とオーケストラの両方を持っているのは、兵庫県と水戸市だけだということです。その片方である水戸市がこうやって活動を活発に続けてくれているというのは、地元出身の僕としては頼もしいし、嬉しいことです。子供の頃、水戸にこんなものができるとは予想もしていなかったですからね。とてもありがたいと思いますね。どんどん先鞭をつけ過ぎたくらいの存在だから、これからも全国の文化行政を先導していって欲しいと思います。
――最後に水戸の聴衆に向けて、メッセージをお願いします。
水戸の音楽愛好家の皆さんが水戸芸術館を育てていると同時に、水戸芸術館が愛好家の皆さんと歩みを一緒にして、お互い育てあっていると思います。また他の地域の話をして悪いのですが、僕は金沢の仕事もしていますが、金沢は本当に文化が地に、足についているところです。それは、どこかの為政者や行政指導者が、よく「来年から文化の年にしましょう!」とか「来年から文化を目指しましょう!」とか言うけれど、文化というのは、それほど簡単なものではない。すぐに結果が出ないからって評価を云々する分野ではないですよ。金沢は、江戸時代に加賀の前田家が、外様であるが故に江戸幕府からもらう百万石を軍備には使えないから文化に注ぎ込んできた。そのために文化が育った。能楽、陶芸、漆器、金箔とかね。金沢に行くと「空から謡が降ってくる」っていう言い方があります。あそこは加賀宝生という能楽の流派の本拠地ですが、植木屋さんや左官屋さんが、謡曲を歌いながら壁塗りしたり植木をいじったりしているということです。本来は武家のたしなみである能楽が広く伝わって、植木屋さんや左官屋さんでも愛好するというくらい、足が地についているということなのです。だからこそ、金沢21世紀美術館もオーケストラ・アンサンブル金沢も見事に根付いているわけですよね。
水戸も同じ立場になり得ると思います。弘道館には音楽という学問があった。水戸というところには、たとえば光圀公だって副将軍と言われながら一方で大日本史を編纂したりした背景があるのです。そういう土地の人たちは文化をたしなむ風土が、体の中の当然の血肉となっているはずだと思います。是非、そういうことを自負して、芸術館とともに歩んでいただきたいと思うし、それでこその水戸市民であって欲しいと思います。
2019年11月29日水戸にて
聞き手:中村 晃






