- 演劇
2018-07-04 更新
水戸子どもミュージカルスクールレポート④
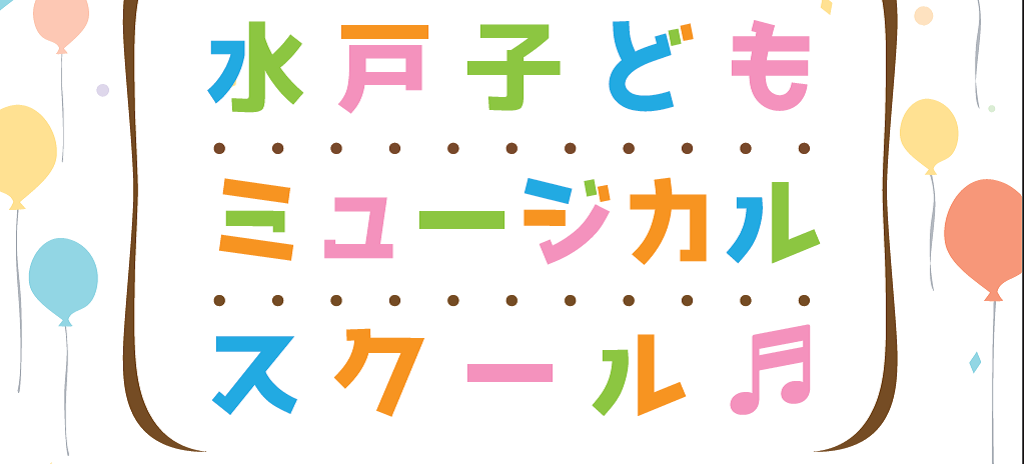
今年度で6期目を迎えた『水戸子どもミュージカルスクール』
井上芸術監督のスクールレポート4回目は、7月1日のレッスンの様子です。
========================================
梅雨が明けての四回目のレッスン。
この時期は、暑くて体力も消耗しがちですが、室内外の温度変化が激しいので、体調管理も大事なレッスン項目になってきました。
水戸子どもミュージカルスクールの特徴
今回は、私の経験から俯瞰して、このスクールの特徴を考えてみるところから始めたいと思います。
一口に、一流の講師といいますが、どの部分をもってそういうのかと言うと、主にその指導におけるキャリアや実績を言うことが多いと思います。もちろん、このスクールのコーチの皆さんは、その点、日本でも有数の方と思っております。
しかし、私が注目するのは、もう少し別のところです。
舞台で表現者として生きるということは、なかなか厳しいものです。
やりたいという気持ちだけでは認められませんし、さまざまなスキルも多く要求されます。
体力も気力も使い切っても、演出家などにはまだ足りないと言われることもあります。
つまり、表現するということは、常に自己ベストを出し続けることを要求されるものなのです。
そのためにどうしたら良いのかと、身も心も使い続けるその日々は、実にハードなもの。
時には悔しくて眠れない夜が続いたり、歯を食いしばってコツコツ積み重ねた日々があるはずです。
そしてそれを続けることができたのは、ミュージカルや舞台への強い愛情があったからと想像しますが、それでもよっぽどタフじゃないと続けられないことだと思います。
スクールで朗らかに優しく指導して下さるコーチの皆さんは、そうした経験を経てきていらっしゃいます。
つまり、たくましきサバイバーなのです。
そのサバイバーたちが、自分が身に着けてきたことや実感したことを、惜しみなく、参加者たちに注いでいます。時に厳しい言葉もありますが、でも、それはそんな経験から産まれた間違いのない言葉です。
今まで三回のレポートでも、講師の皆さんの言葉をいくつか紹介してきましたが、レッスンを受ける参加者たちは、その言葉の強さや重みを一生懸命受け止めようとしています。
こんな関係性のあるスクールであることが何よりだなあ、といつも思っております。
ここがすごいねっていつも思っておりますので、そのあたりをお伝えしたく書かせていただきました。
レッスン開始!
さて、そんなスクールの四回目のレッスン。
メンバーたちがどんどんコーチの言葉に敏感になっています。
仲間同士でお喋りしていたかと思うと、コーチの一言で口を閉じ、コーチに注目をする。
いわゆるオンとオフがはっきりしてきた。そしてコーチの指示とその意味をしっかり理解して行動するようになってきました。
今日は、通常のレッスンに加えて、これから作品を作るための新しい共同作業が高城ヘッドコーチから説明されました。
最初にこんな説明と投げかけがありました。
「そもそも舞台上で役を演じるということはどういうことか。
物語はどういう構造をもって書かれているのか。
台本にはセリフとわずかなト書きしか書いていないが、そこに書かれている世界や登場人物は、
どういうものなのか。
そうしたものを踏まえて、自分たちはどんな世界を作っていくのか。」
そこで、参加者は五つのチームに分けられ、そして台本のあるシーンが指定され、それを自分たちなりにシーンとして作るように指示されました。
誰がどの役をやるのかもチームで決定し、そして自分たちなりに作ってみてと。
これから数回にわたって、そのシーンつくりをしながらレッスンが進みます。
舞台作りは一般的に、演出家が世界観と構造を作って、俳優やスタッフとそれをリアルにする作業を重ねます。
それが稽古ということになりますが、プロになればなるほど、それはお互いのアイデアで作られていきます。
でもこうした初心者だらけのスクールでは、演出家が決めた世界観をそのまま実行することがほとんどです。
参加者は、自ら発想しそれを形作る作業に慣れていませんし、そもそもそれ自体時間がかかることなので、時間の都合から決めたことを迅速にやるだけの運営になりがちなものです。
グループ練習
さて、この作業は短いながら、芝居づくりのすべてのエッセンスが入っています。
作品を考え、役を考え、そしてそれをリアルにするアイデアを自らが出していく。
そしてみんなと調整し、人に見てもらうという前提で実現していく。
これがどこまでいけるかが楽しみなところです。
メンバーの何人かは何度かの公演をやっていますがその体験をどう生かせるか、初めての人たちの新鮮なアイデアがどう取り込むのか・・。たくさん考えて、たくさんの試行錯誤も必要です。
その前には、自分の考えをしっかり人に伝えて分かってもらう必要もあります。その調整にも手間取るでしょう。
時間のかかる作業ではありますが、こうした作業が仲間とのコミュニケーションが深まり、その結果お互いの違いを尊重していく協働作業になって行くことと思います。
最後の高城ヘッドコーチの一言が面白かったです。
「コーチのわたしがやらないだろうことを、やって」。
つまり、私の目を気にしないで自由にやれってことでしょうが、メンバーみんなは一表現者として扱われた瞬間だと思いました。
さて、どんな答えをもって来週やってくるでしょうか? レッスンもますます目が離せなくなってきました。
【記:井上桂(ACM劇場芸術監督)】
高城ヘッドコーチのコメント
7月に入りました!「グループ練習」開始です。
毎年少しずつ内容を変えていますが、目的や願いはいつも一緒。
作品づくりをより身近に感じてもらい、主体的に参加する楽しみを見つけて欲しいということなのです。
私は、このグループ練習の中で受講生のみんなの中にある「創造力」をいくつ見つけられるかなぁ〜
今からとても楽しみです♫
梅雨も明けてアツい夏が到来してますが、ミュージカルスクールも負けじとアツくいきましょう!
高城信江
↓↓高城信江ヘッドコーチのブログにもスクールの様子が紹介されています!
https://ameblo.jp/niji-okurimono/entry-12381102324.html






