- 音楽
2021-09-18 更新
【インタビュー】水戸芸術館のパイプオルガンができるまで②画家の兄との欧州旅行をきっかけに…オルゲルバウマイスターへの道
(マナオルゲルバウ代表・中里威さん)
水戸芸術館にある国産最大級のパイプオルガンのルーツを辿るべく、マナオルゲルバウの工房を訪ねてインタビューを行った。第2回に登場するのは、マナオルゲルバウのもう一人の代表、中里威さん。画家の兄・斉さんとのヨーロッパ旅行でオルガンの素晴らしさに開眼。そこからまるで何かに導かれるように、教師からオルガン造りの道へ。渡欧して修行を積み、やがてオルゲルバウマイスターになるまでの出会いの数々について、気さくに語ってくださった。取材・文=高巣真樹 写真=山崎宏之
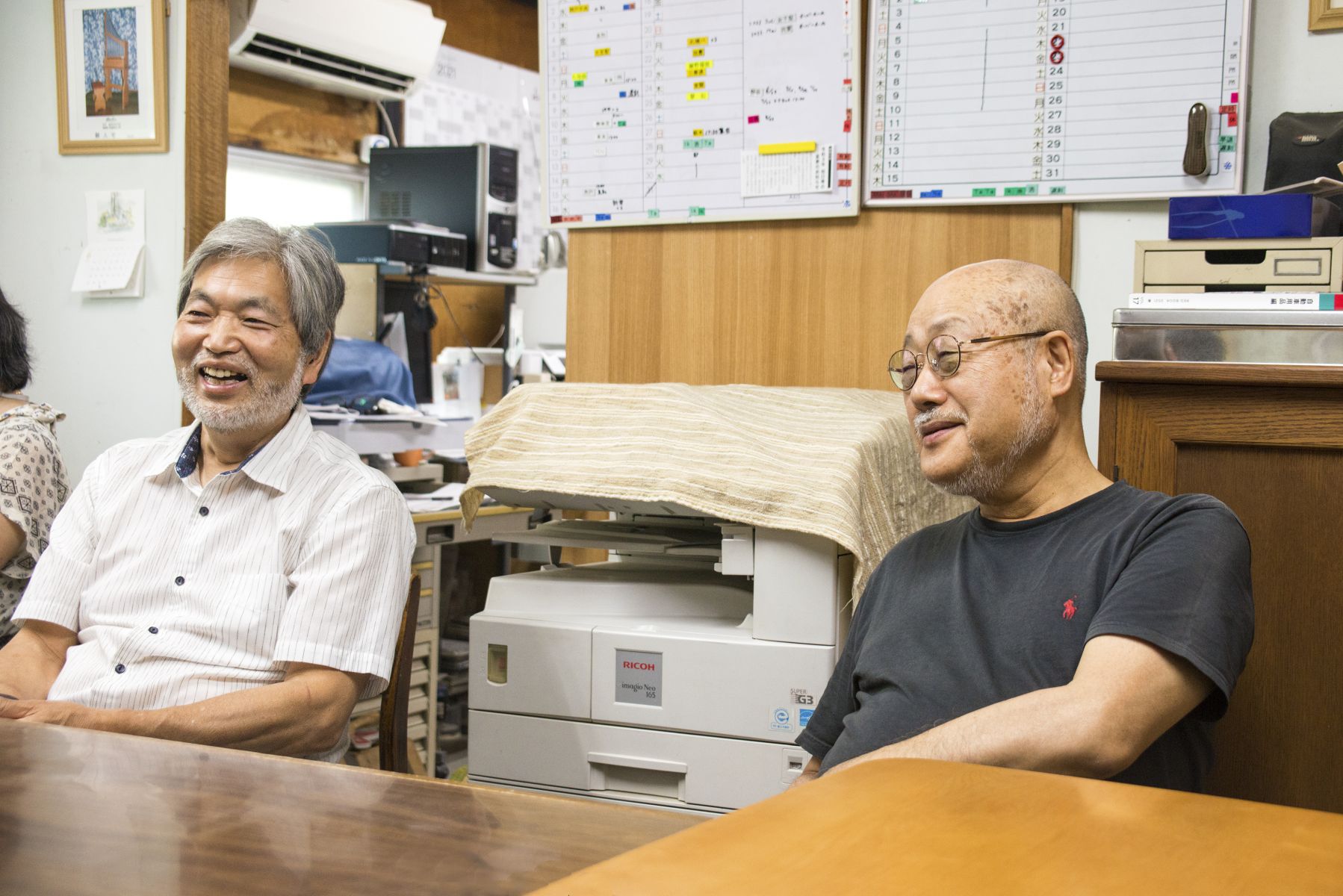
左・中里威さん、右・松崎譲二さん
<目次>
画家の兄とのヨーロッパ旅行をきっかけに
中里:私は中学からずっとコーラスをやっていました。中学高校は桜美林学園で、大学は玉川大学。卒業後は玉川学園中学部で数学の教師をしていたので、町田から一歩も出ない人生でした。画家の兄〔註・中里斉(ひとし)さん〕は、アメリカから一時帰国して多摩美術大学の講師をしていたのですが、学生運動で学生の味方をしたらクビに。それでニューヨークに戻る時、「おまえは町田しか知らないな。ヨーロッパに行くから一緒に来い」と言われたんです。それが1972年、就職1年目の夏休み。部長に相談したら、「45日間の研修旅行として行ってこい」と言って旅費も出してくださいました。
◎中里斉(なかざと ひとし)さんWEBサイト
それで松崎と同じように、船で3泊4日かけてナホトカに行き、シベリア鉄道でハバロフスクまで一晩。それから飛行機で8時間かけてモスクワへ。そしてショパン号でワルシャワ、プラハ、ウィーンをまわり、南下してイタリア、スイス、ドイツ、フランスを巡りました。美術館や教会によく連れて行かれて、私はクリスチャンだから教会は喜んで行きました。そのときにオルガンの素晴らしさを知りました。帰りはパリで別れ、私は北欧旅行へ。それからレニングラード経由で帰国しました。
教師生活2年目には、宇都宮のピアノ工場に1か月研修に行かされ、その経験を元に生徒たちとピアノ制作をしたんです。そのときに楽器作りの面白さに目覚め、教師よりも向いているんじゃないかと思いました。そのとき自然にオルガンがひらめきました。ちょうど私の生徒のお父さんが玉川大のオルガン科教授(富永哲郎氏)だったので相談したら、彼はオルガンビルダーの辻宏さんとほぼ同期。辻さんと奏楽堂のオルガンの中に潜って修理したりしていたらしいんです。「私も実はオルガン屋さんになりたかったけどならなかった。君はぜひやってみてくれ」と励ましてくださいました。
教師からオルガンビルダーへ
教師2年目が終わる頃には、絶対にオルガン造りをやると決めました。当時は数学や物理、柔道、水泳を教えていて忙しかったのですが、オルガン屋さんになるために辻さんに話を聞きにいったら、「オルガン作りは木工が基礎。日本の優れた木工を勉強していくといい」と言われました。それで知り合いの木工所に行ったら、社長が契約書を用意して待っていました(笑)。それで教師3年目が終わるときに学校をやめて、4月1日から木工所の見習いになりました。
妻は当時、富永先生にオルガンを習っていて、「家でもオルガンが弾きたい」と言うので、クロダトーンという会社に中古の楽器があるか聞きに行ったんです。そこでオルガン造りに興味があることを話したら、「5月に札幌でオルガンを組み立てるから見に来ないか」と誘ってくださいました。それで札幌北一条教会で通訳などお手伝いしていたら、ペーター・パウル・ケーベレというオルゲルバウマイスターに出会いました。その後、「いつ来てもいいですよ」という手紙をいただきました。オルガンを買いに行ったはずが、造る道に進んでしまったんです(笑)。木工所には1年間勤めて、一番腕のいい人の助手として、嫁入り道具の箪笥を任せてもらうまでになりました。

ドイツでの修業時代
中里:ドイツに行ったのは1975年4月。シュヴェービッシュ・グミュントという、城壁が残る田舎町にあるケーベレ社で、まずは丁稚奉公。普通は3年半やりますが、私は木工をやっていたので3年に短縮されました。職人試験を受けるために職業訓練校で社会科、数学、音響、物理など勉強しながらドイツ語を覚えました。数学の試験のときには、僕が日本で数学を教えていたのをみんな知っていたので、よく答案を見られていました(笑)。
渡独から2年8か月後にはオルガン職人資格を取得しました。その試験会場はマイスターの学校でもあり、松崎もちょうど同時期そこに通っていたので、先生の紹介で彼と初めて会いました。私は1979年9月に家族と一時帰国し、恵泉女学園や札幌北一条教会が買った新しいオルガンの組み立てをして、12月に再びドイツへ。80年にルードヴィヒスブルクのマイスター学校に入学しました。そこで僕の隣に座っていたハンス・ウルリッヒ・エルプスレーという人がハンブルクのベッケラート社の人で、彼の誘いで会社見学に行ったら、社長が契約書を用意していました。ちなみに息子は1977年、娘が1980年に生まれたので、3人いる子どものうち、2人はmade in Germanyですね(笑)。

ルードヴィヒスブルクのマイスター学校時代(本人提供)

1980年8月にハンブルクに移住してからは、マイスターとしていろんな組み立てを担当しました。そのときに国立音楽大学から、ベッケラート社にオルガンの注文をいただいたので、組み立て要員として日本行きが決まりました。社長が「正規の旅費をあげるから自由に使っていい」と言ってくれたので、1982年8月に家族と引き上げて、9月から国立音大で半年間、組み立てや整音をやりました。
たけし&ジョージ!? 松崎さんとの出会いと会社設立
その後、大規模な仕事の時には、私のひと月前に帰国していた松崎と助け合いながら仕事をしていたんです。そんな中、東京藝大の旧奏楽堂の話を機にオルガン制作会社を立ち上げることになり、1985年12月、松崎と中里の頭文字をとって「マナ」オルゲルバウを設立しました。二人の下の名前が威(たけし)と譲二(じょうじ)で、ビートたけしや所ジョージが売れ始めたときだったから、たけし&ジョージという社名も考えたけど…(笑)。当時、ベッケラート社のオルガンが松本市音楽文化ホールにも入ることになり、平日は旧奏楽堂、週末は松本で仕事。そうこうしているうちに会社が育っていったんです。

マナオルゲルバウにて。工房には木材やパイプを加工する数多くの道具や機械があり、熟練の職人たちによる非常に緻密な仕事の積み重ねでオルガンが造られていることが伝わってくる。




整音作業を説明してくださった松崎さん。手元の鍵盤を押して音を出しながら、パイプの音色を丁寧に調整する。
中里:磯崎新さんとうちの兄はちょっとつながりがあって。磯崎さんが1988年に埼玉に武蔵丘陵倶楽部というゴルフ場のクラブハウスを造ったとき、兄が壁画を頼まれたんです。そのときに、弟がオルガン制作者であることを話してくれていて。それで磯崎さんが、僕たちに水戸のオルガン制作を任せてみたいと考えてくださったようです。水戸市長だった佐川一信さんもとても良い方で、僕たちを信頼してくださいました。
◎インタビュー第1回「張り切って引き受けた一世一代の仕事」は こちら
◎インタビュー第3回「誕生、そして市民に愛されるオルガンへ」は こちら






